――これは俺の、たった一度きりの初恋の記録だ――
38歳、女性経験なし。
185㎝の身長を持て余し、女の子と手をつないだ記憶なんて、学生時代のフォークダンスだけ。
…そんな俺が、人生で一度だけ、本気で人を好きになった。
もちろん、それまでも、誰かを好きになったことはある。
けれど、俺は、いつも“動けなかった”。
でも、その時の俺は──もう、動かずにはいられなかった。
温泉旅館で働いていた、あの季節。
そこで俺は、まるで予告もなしに、人生を変える“出会い”を迎える。
彼女の名は──Y
この恋は、やがて俺の人生を、大きく動かすきっかけとなる。
最悪の出会い【職場で出会った6歳年上の既婚女性】
すべては、転勤から始まった
――2022年の夏の終わり。
Yと出会ったのは、旅館に勤務していた頃。
当時の俺は38歳、彼女は6歳年上のパートスタッフだった。
最初に勤務していた旅館から、別の旅館に転勤になり、そこで彼女と初めて顔を合わせた。
異動前の支配人から、彼女のことは少しだけ聞かされていた。
「やたら気が強いパートの女性がいる」と――。
俺がそれを知ったのは、配属されてすぐのことだった。
舞台は小さな温泉宿
俺が配属されたのは、地方の小さな温泉宿だった。
フロントには支配人のDを含む正社員が3人(俺はその1人)、
清掃担当のパートが2人(Yはそのうちの1人)、
それを補助するアルバイトの主婦や学生が数名。
厨房には料理人がいて、夜は夜警のおじさんが見回りをしていた。
全体的にこぢんまりとした職場で、スタッフ同士の距離も近い。
良くも悪くも、誰かが何かをすれば、すぐに噂になるような、そんな環境だった。
そんな場所で、俺は既婚女性に本気の片思いをしたんだから……
「我ながら、よくやったもんだ…」と、書きながら思う。
・・・何だこの女?
配属2日目、Yはフロントにいる俺のところにズカズカとやって来るやいなや、俺に早口でまくしたてた。
「あなたは正社員かも知れないけど、この旅館はこれまでこういうやり方でやってきた。だからそうしてもらう。」
という内容だった。
これには俺も
(・・・はあ…?なんだコイツ・・・?)
となるわけだ。
俺はすかさず言い返した。
「これまでの方針は分かりますが、やってきたばかりの正社員に対して、パートのあなたが組織のあり方について指示をだすのはおかしいんじゃないですか?」
彼女は特別怒った様子も見せなかったが、やがてプイっと清掃業務に向かって行った。
・・・こうして彼女と俺の関係は最悪の形から始まった。
おかしな職場、そしてY
職場に慣れるまで
Yに対して嫌悪感をもったまま業務にあたる日々が続いた。
また何か言ってくるんじゃないかと、不安半分、イライラ半分といった感じだ。
だが俺の気持ちとは裏腹に、特に何事もなく進んでいった。
時々彼女が業務関連の依頼をしてきたり、俺の仕事の様子を監視しているようなそぶりはあったが。
そうこうしながら俺は仕事に慣れていき、少しずつ、Yとこの旅館のことを知っていくことになる。
行動派のY、そして驚くべき事実
彼女は本当によく働く女性だった。
朝やってくるとあいさつもそこそこに、その時点のチェックアウト状況を確認すると、さっさと客室の清掃に行ってしまう。
仕事が終わると、几帳面に必要な備品や連絡事項をメモにきれいにまとめて、気づいたらいなくなっている。
俺との接触も必要最低限だった。
俺は肩透かしを食らった気分になりつつも、どこか安心していた。
そんな中、俺は信じられないような事実を知ることになる。
なんと、Yは清掃の学生アルバイトを自分で集めてきていたのだ。
彼女は団地に住んでいて、そこで近所の高校生に声をかけ、不足しがちな人員を補っていたのだ。
本来なら支配人や人事担当がやるようなことを、彼女が仕切っていたわけだ。
はっきり言って、普通の職場じゃ考えられない。
でも、それが当たり前になってしまうような、ちょっと異常な職場だった。
(これなら初対面の発言も納得できるな・・・。)
と思った俺は、彼女に興味を持った。
(間違いなく俺より働いている。
最初にきつく反論しすぎたかもしれない。)
そんなことを考えながら、俺は徐々に彼女を意識するようになっていた。
でも俺は何もできなかった。
声をかける勇気もなくて、ただフロントのカウンター越しに、彼女の背中を見送るだけだった。
1冊の手作りのマニュアル
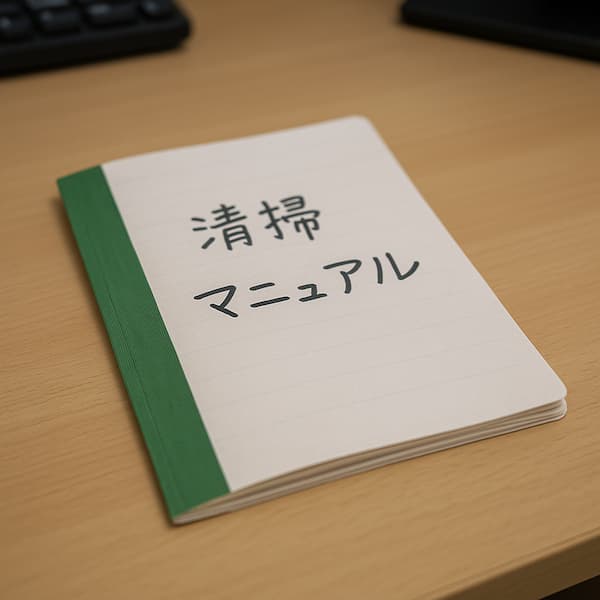
(※これはイメージイラストです。実際のものではありません。)
必要最低限の人員で回している旅館ということもあり、俺にも客室清掃の仕事が回ってくることが出てきた。
ある日、事前に知らせを受けていた俺は作業用の私服を持って出勤した。
そして、フロント横の事務室の机に冊子が1冊置いてあることに気づいた。
Yの文字で、
『清掃マニュアル』
と書かれている。
めくってみると、10ページほどに渡り、客室清掃の手順や注意点が細かく記載されている。
ところどころマーカーや、かわいらしいイラストで、わかりやすくしている。
もちろん、会社がこんなものを用意してくれるわけもない。
彼女が業務時間外に作ったものだろう。
冊子にしたところで、質素なものだ。
使い終わったA4用紙を半分に折って、それを重ねてホチキス止めし、そこを色付きテープで補強してある。
・・・だが俺は、彼女のいじらしさというか、いたいけさというか、感じずにはいられなかった。
ページをめくるたびに、彼女の几帳面さと繊細さが伝わってくる。
こんな人が、同じ職場にいるんだ――そう思った瞬間、胸の奥がじんわり熱くなった。
気づけば、彼女のことが頭から離れなくなっていたんだ。
2人の距離が縮まるきっかけ ~Yと支配人Dの対立~
人員不足がトラブルの火種
2022年の年末、旅館内でちょっとしたいざこざが発生した。
もともと最小限の人員で回していた旅館だったため、年末の繁忙期の人員のやりくりに苦心していた支配人のDは、
清掃係のパートであるYや他のパートに年末年始の食器洗いの仕事を依頼した。
普段であればYが応じてくれることもあったのだが――年末年始だ。
彼女たちも家庭がある。
Yはパートの代表として「外注のヘルパーに依頼してほしい」とやんわり断りを入れたのだが、Dが承諾しなかった。
そして折り合いがつかないまま年末に近づいていった。
そして事件が起きた。
にらみ合うYとD
年末が差し迫ったある日、俺が食堂の清掃をしていると、フロントから言い合う声が聞こえてきた。
俺が慌てて様子を見に行くと、YとDが言い争っている。
どうやら、例の年末年始の話をしているようだ。
身長160㎝のYが、果敢にも180㎝を超えるDに食って掛かっている。
その目は強気だった。
だが少し潤んでいるようにも見えた。
Yの横顔はとても綺麗だった。
俺はすでに、彼女に惚れていた。
最終的にDが折れ、
「もう頼まない!」
と言ったところで言い合いは終わった。
Yは出勤簿に退勤時間を書き込むと、足早に従業員用ロッカーの方へ去っていった。
俺はDをなだめると、急いで彼女のあとを追った。
(補足)殺気立っていた職場
当時は新型コロナウイルスの影響で始まった「全国旅行支援」の真っ最中だった。
問い合わせの電話、チェックイン時の書類確認、商品券の交付作業など、事務量が圧倒的に増え、特にフロント内は殺気立っていた。
Dのやり方は少し強引だったかも知れない。
だけど彼の多忙を横で見ていた俺としては、今回のことを責める気にはなれなかった。
二重スパイの誕生
「Dさん、何もあそこまで言わなくてもいいのにねえ・・・!」
ロッカーの前でエプロンを外している彼女に追い付いた俺は、あわててなだめようとした。
「もういいんです‼」
彼女は怒っていた。
そしてさっさと帰ろうとしている。
焦った俺は無責任な言葉を放った。
「……俺が、やりますから。俺、なんとかしますんで……!」
ほんの一瞬だけ、彼女の手が止まった。
何か言いかけて、やめたような……そんな気がした。
だがすぐに荷物を持って帰っていった。
・・・この日から俺の二重スパイとしての生活が幕を開ける。
俺は翌日から、Dの機嫌を取りつつも、彼を共通の敵とすることで、徐々にYとの距離を縮めていくことになるのだ。
二重スパイの日々
結局、年末年始は外部のヘルパーを呼ぶことで、なんとか回った。
それでもかなりハードな数日間だった。
あの日以来、DはYに厳しく接し始め、若干パワハラ気味な行動を取るようになっていった。
俺はというと、徐々に彼女と打ち解け始め、Dをダシにしながら確実に俺たちの仲は深まっていった。
「俺が不在のときに、Dさんに何か言われませんでしたか?」
なんてヒーローを気取りながら、Yと接していた。
DにはYの無難な情報を与えつつ、その反応を逆にYに伝え、笑い話にしたりした。
彼女と過ごす幸せな時間が、罪悪感を上回っていた。
彼女の何気ない一言が、頭の中で何度もリフレインした。
毎朝、彼女がフロント横の事務室に入ってくるのが楽しみだった。
俺の視線に気づかないまま書類に目を通す姿。
どれもが、俺にとっては意味のある風景になっていた。
そして俺は、ある決心をする。
俺が初めて女性に連絡先を聞いた日
──2023年1月18日。
38歳の俺は、人生で初めて女性に連絡先を聞いた。
その日、俺はフロントでチェックアウト業務をこなしながら、彼女の出社をじっと待っていた。
時計の針が進むたびに、鼓動が速くなっていく。
そして、ついにその時が来た。
彼女が出社してきた。
俺はぎこちなく挨拶を返しながら、フロントの脇の事務所でチェックアウトや予約情報の確認をしていた彼女の後ろ姿を見つめていた。
(さあ来たぞ、動け、俺。)
足が震えていた。
だが立ち上がり、俺は声をかけた。
冷静に話すつもりだったが、声が裏返っていたかもしれない。
「連絡先、教えてもらえますか……? 仕事のやりとりもしやすくなると思うんで……」
用意していた、とってつけた理由だ。
彼女は少し驚いた様子で、それでもエプロンのポケットからスマホを取り出した。
だが次の瞬間、こう言った。
「でも……内線で連絡くれれば大丈夫ですよ?」
一瞬、心臓がきゅっと縮んだ。
「……そうですよね。」
俺は負けそうになり、フロントの椅子に腰を下ろした。
彼女はスマホを一度しまった。
だが、その目線は俺の方を向いていた。
(動け、俺──ここで動かなきゃ、また何も変わらない!)
俺はもう一度立ち上がった。
そして、少し早口になりながら言った。
「・・・・・・やっぱり…リアルタイムでチェックアウト情報も送れますし。Dさんの前では言いにくいことも、こっそりやりとりできますよ!」
彼女は一瞬だけ間を置いたが、黙ってまたスマホを取り出し――
俺とLINEを交換してくれた。
客室清掃に向かった彼女の背中を見送った後、フロントに一人残った俺は、
スマホの画面に表示された彼女のLINEアカウントのプロフィールを見ていた。
にやけていたかもしれない。
いや、確実ににやけていた。
そのとき、チェックアウトのお客様がやってきた。
俺は対応しながら、早速彼女に初めてのLINEを送った。

〇〇です

303、OUTしました
──これが、俺が彼女に送った、人生で初めてのLINEだった。
(中編につづく)








